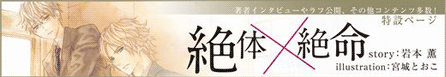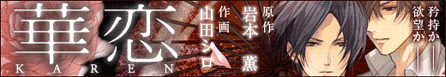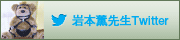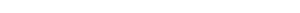【いまから部屋に来られないか?】
レンからのメールを受信したのは、土曜の深夜零時過ぎだった。三十分前に出先から戻って来て、あとはシャワーを浴びて寝るばかりだったジンは、【いいよ。五分後に行く】とレスポンスを返した。同じ屋敷に住んでいながら、メールでやりとりするのもおかしな話だが、それくらい、この『パラチオ デ シウヴァ』は広いのだ。
エストラニオ一の権力を持つシウヴァ家の当主であるレンとジンが知り合ったのは、レンにしてみれば完全にイレギュラーと言ってもいい、スラムでのトラブルがきっかけだった。年齢が近かったせいもあってか、なぜかレンに気に入られ、今日までつきあいが続いている。スラム出身の自分が、シウヴァのプリンスと友人づきあいをしているなんて、誰に言っても信じてもらえないだろう。しかも現在、自分はシウヴァの宮殿に居候の身だ。そんなことが古巣の仲間にばれた日には、面倒に巻き込まれるのは必至。だから、誰にも話していない。口が固いことがわかっているから、側近のカブラギも、自分がレンの側にいるのを許しているのだと思う。それだけ信用されているのだと思えば、悪い気はしない。生きていくために、裏切ったり、裏切られたりが当たり前のスラムでは、「友情」や「信頼」なんて絵空事だった。そんな環境で生まれ育った自分が友人を持つ日が来るなんて、思ってもみなかった。だがいまは、少なくともジンのほうはレンを友人だと思っているし、彼がピンチに陥ったなら、いつだって力になりたいと思っている。
(面と向かっては言わねーけどな)
自分はそんなキャラじゃないし、言わなくても、レンには伝わっているはずだ。
ひさしぶりに過去を回想しながら美術館みたいな廊下を五分ほど歩いて、この屋敷の主の部屋に着いた。当主の部屋だけあって、扉からして立派だ。コンコンコンとノックすると、「どうぞ」といらえがある。ドアを開けたジンは、いきなり黒い獣の頭突きに出迎えられた。
「うぉっと」
「グォルウウウ」
唸り声だけ聞けば恐ろしいが、二年以上のつきあいで、甘えているんだとわかる。
「こら……びっくりさせんなよ」
丸い頭を脚に擦りつけてくるブラックジャガーの首を軽く叩いた。初めて見た時は、腰を抜かしそうに驚いたが、いまでは黒い獣に友情めいた感情まで抱いているのだから、不思議なものだ。
「エルバ」
名前を呼ばれたエルバがタタッと引き返していく。その姿を視線で追ったジンは、ソファに座る部屋の主を見た。プリンス・オブ・シウヴァの称号にしい、気品としさを併せ持つ、自慢の親友。だが、直後に眉をひそめる。予想外の人物が、もう一人いたからだ。
「なんだ……来てたのか」
「ああ、さっきな」
答えた男はレンの横に腰掛け、長い脚をゆったりと組んでいる。黒い髪に灰褐色の瞳。ぱっと見はアジア系に見えるが、骨格や彫りの深さは欧米のそれだ。人種のるつぼであるエストラニオにいては珍しいことではない。
ヴィクトール・・。鏑木家の当主で、レンの側近。いや、元側近と言うべきか。
「どうした? 嫌そうな顔をして」
男が、訝しげに片眉を上げる。
カブラギが嫌いなわけではない。むしろ好きだ。男らしくて頼もしく、誠実でクレバー。ろくでもない大人ばかり見てきて、ひねくれた自分でさえ、一目置かざるを得ない。なおのこと、素直で純粋なレンがかれてしまうのも、うなずけるのだ。
そう──レンは、この男にぞっこん惚れている。主従、さらに男同士というハードルを乗り越え、現在二人は恋人同士なのである。
「だってさ、俺、お邪魔じゃん」
ジンが肩をすくめると、カブラギが笑って呼んだ。
「そう言わずに、こっちに来てくれ」
レンも笑って、「鏑木がおまえに土産を持って来てくれた」と招く。
「珍しいワインが手に入ったんだ」
カブラギが、ローテーブルの上のワインボトルを手で示した。
「ジャブチカーバのワインだ」
ジャブチカーバといえば、ジャムやリキュールに使われるブドウ属の樹だ。房で実るぶどうとは異なり、幹に実がつく。ジャブチカーバで作ったワインなんて初めて聞いた。
興味をそそられたジンは、ローテーブルに歩み寄ってボトルを摑んだ。エチケットを読む。
「【Água de Beber】。—おいしい水—」
「イパネマの娘」の作詞家で知られるヴィニシウス・ジ・モライスのボサノヴァのタイトルだ。
「ブラジルの小さな村で少量しか作られない稀少なワインだ。たまたま手に入ったんで、おまえに吞ませたいと思ってな」
ジンのワイン好きを知っているカブラギが、うれしいことを言う。
「それならそうと早く言えよ」
ニッと笑い、ジンはソファと向かい合わせの肘掛け椅子に腰を下ろした。カブラギがワインを抜栓し、赤い液体をグラスに注いだ。
「テイスティングしてみてくれ」
グラスを手に取ったジンは、スワーリングしたワインを一口含む。
「うん……甘さと酸味のバランスがちょうどよくて、美味い」
「よかった。好きなだけ吞んでくれ」
グラスになみなみと注がれ、ぐいっとった。物心つく前から吞んでいるジンにとって、ワインはまさしく「水」のようなものだ。カブラギとレンも「なかなか美味いな」「うん、吞みやすい」などと言い合いながら、グラスを傾けている。さほど酒が強くないレンは、ほどなくほろ酔い加減になり、目つきがとろんとしてきた。その潤んだ目で、隣の恋人を熱っぽく見つめる。
(おー……見てる、見てる)
カブラギも当然、その熱い眼差しに気がついているだろうが、ジンの手前、無視を決め込んでいるようだ。
つれなくされても、「大好き」オーラを出し続けるレンがいじらしく、かわいそうになったジンは、「ちょっとトイレ」と言って席を外した。パウダールームに入り、スマホをって時間を潰す。
(そろそろか?)
頃合いを計り、パウダールームを出た。主室に戻ろうとして、視界に飛び込んできた光景に、びくっと肩を揺らす。
ソファの二人がキスをしていた。ジンの位置から見えるのはソファの後ろ側だが、レンがカブラギの首に腕を絡ませるようにして唇を合わせているのはわかる。
(……いつまでチューしてんだよ)
内心で舌打ちをして、パウダールームに戻るか否かを思案していると、足許にエルバが寄ってきた。二人に相手にされないので、ジンに遊んでもらおうと思ったようだ。
「グォォルルル……」
「あ、こら……しっ」
静かにしろとめたが、エルバはお構いなしに喉を鳴らし続ける。
カブラギがその音に気がつき、唇を解いてレンを離した。不満そうに唇を尖らせたレンが、次の瞬間、こっちを見る。ジンに見られていたことを知ったその顔が、カーッと赤く染まった。
「ご……ごめん」
気まずそうに謝られ、ジンは前髪を搔き上げる。
「いや……こっちこそ、お邪魔だし、そろそろ俺は部屋にもど……」
「駄目だ!」
大きな声を出して立ち上がったレンが、こっちにダッシュしてきたかと思うと、ジンに抱きつく。
「レ、レン!?」
「もう少し一緒にいてくれ!」
(酔っ払いかよ)
熱っぽい体を押しつけられ、困惑したジンは、ふと視線を感じて顔を上げた。カブラギと目が合う。灰褐色のは、いつになく険しかった。
(うわー、嫉妬メラメラ)
どんな時にも動じない大人なカブラギの、人間くさい一面を見た気がして、親近感を覚える。
「わかったって。一緒に吞もうぜ」
肩を叩いてレンをめたジンは、エルバを引き連れ、カブラギが待つソファまで戻った。これは朝までコースだな、と腹をくくりながら。
終